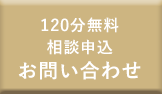アーネスト・ヘミングウェイを想って
シュシュと初めて逢ったとき、彼の手には「アイランド・イン・ザ・ストリーム」があった。その後半といえば「中編小説」である「老人と海」である。
作品の内容は、老人漁師サンチャゴ。彼をきにかけるのは助手の少年くらいだ。サンチャゴはカジキマグロを漁獲するが漁港に運ぶまでに様々な敵に襲われて、カジキマグロは骨だけになってしまったのだ。そう、サンチャゴとカジキマグロは実は同列の存在なのだ。
その戦いを知るものはいない。ただ、少年が理解を示すだけだ。老人は究極的に孤独だ。誰も助けに来ない中、格闘を続けている。そして、決してあきらめない。それは、彼は途方もない孤独を経験し彼を慕ってくれる少年を幾度も思い出しながら、決して悲観的にならないからだ。そんなサンチャゴの姿は、「人間はなぜ生きるのか」という疑問を我々に提示する。
アイランド・イン・ザ・ストリームを読んだのは、もう20年も前だ。その時は男の誇りや闘志など、ヘミングウェイのトレードマークといえる男性的なテーマだと思っていた。しかしながら、シュシュは、別のパースペクティブを持っていた。彼と議論をして、自分も年齢を重ね、そこには、「生きている限り必ず老いる」「必ず死ぬ」。若いころの読み方とは、必然的に異なってくる。
思うに、ヘミングウェイは、作家志望であったが新聞記者になったうち、戦時中は従軍し重傷を負う。戦後は、ヘミングウェイは、戦争に幻滅したアメリカ人らとともにパリに住む。この時代に、ヘミングウェイの文体は確立されていったといえる。
ヘミングウェイが、スペイン内戦でのゲリラたちの物語「誰がために鐘は鳴る」がある。これは多くの人から、ある意味で、ヘミングウェイのコード・ヒーローと呼ばれる人物、人生に幻滅していてストイックで、暴力や逆境に直面すると自分のコード、つまり掟に氏tがって気品と高潔さを発揮する男性―ヘミングウェイのこうした作品は幼少期のように、母親から男児としては嫌われて女の子として育てられた過去の反動かもしれない。
だが、改めて、甥っ子にいおう。僕の「老人と海」の読み方は一面的だった。僕はコード・ヒーローものとしか思えなかった。だが、彼の作品の中にはニヒリズムが存在している。「老人と海」が孤独とむなしさ、それでも手放してはならない誇り、ヘミングウェイの人生観を投影したこの作品は、彼のストーリーテラーとしての力量が発揮されたといえる。晩年はうつ病と健康の衰えに悩まされ、1961年、ショットガンで自死を遂げた。それでも、現代小説の文体は彼の反復を多用し無駄をそぎ落とす。そんな現代文学にも通ずる影響は今なお残っている。
今後は、ヘミングウェイがこの作品に残した人生観について、単に男らしさを意図的に全面に出しただけ、という誤った解釈を改めて、孤独とニヒリズムという観点からも再考してみたい。