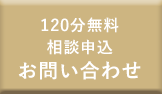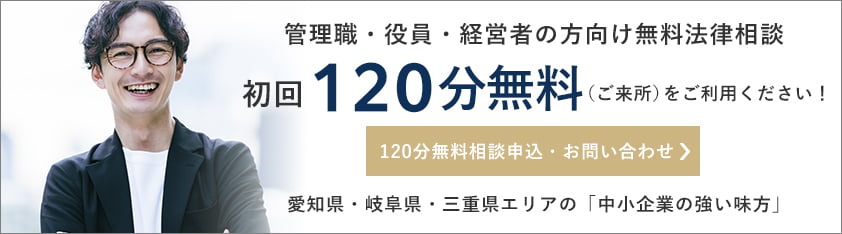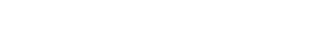お役立ちコラム
8月下旬ころ、東京の東京税理士会館で行われました租税法学会に出席してきました。
学会では、先般の国税通則法の改正が取り上げられており、更正が可能となる期間が5年となり概ね更正が可能となったなどの改正点の報告がされました。
元・立命館大学大学院教授の三木教授は、日本は申告納税方式を採用しているのに申告ミスに対してとても厳しく接しているとの指摘がありました。
昔は、「当初申請要件」という要件があり、最初の申請書に書いてなければ、事後的に更正をすることはできない等厳しい取り締まりの発想での徴税が行われていました。
驚かされるのは国が税金を決めて、国民に課してくる賦課方式を採用している固定資産税などでは、比較的租税訴訟で成果が上げられているということです。
しかし、教授がいわれるように、申告納税制度というのは、国の国民に対する信頼を基礎に成り立っているはずです。賦課をする手間を省くのに協力をしています。
それなのに判例上、救済されるのは賦課方式のもの、固定資産税のものばかりというのでは、本末転倒ではないかという問題意識がありました。
申告納税なのですからミスをするのは当り得ることです。
今回の国税通則法の改正が、本来の理念に立ち返るものとして運用されるよう望みます。
租税訴訟学会の帰りに、フェルメールの絵が2つ、東京上野の都立美術館と国立西洋美術館に来ているということで見学してきました。
「真珠の耳飾りの女」が展示してある都立美術館は、閉館間際というのに長い列ができていて入場できたのは30分後でした。
他方、国立西洋美術館の方は、比較的空いていて、「真珠の首飾りの女」はスムースにみれることができました。
オランダというのは、スペインからの影響力を脱した後、東インド会社を持ち商業が活発化した商業の街でした。
そして、プロテスタントが多いということもあり、絵画は人物画、風景画、風俗画の方につながっていきます。
フェルメールの絵も風俗画と位置付けることもできるでしょうか。
オランダの風俗画をみると、「ヤン・ステーン」という皮肉屋さんの画家の絵をたいてい展示しています。
今回も、左に貧しい人たちが、右の裕福な恰好をしている人物に詐欺にあっている様子など、いつの時代にも、
そのような人物というものはいるものだ、という教訓を述べているように感じます。
こういう中で、「真珠の首飾りの女」は、純粋さを持ち光の描き方という技術的なものではなく、みるものに純粋であることを説いているような気がします。
個人的には、フェルメールの中でも、この絵がもっとも落ち着きを与えてくれる好きな絵ですね。
フェルメールの絵はなかなか日本では、企画展以外見る機会がありません。
9月半ばまでだと思いますが、東京に行かれた際は、お立ち寄りになることをおすすめします。