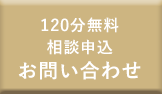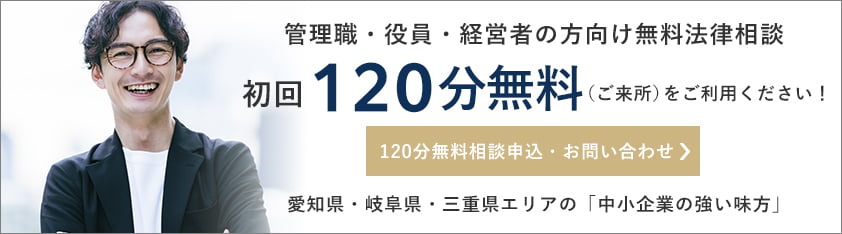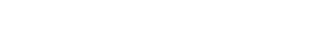お役立ちコラム
これまで裁判員裁判は、2件ほど担当したことがありますが,GW前に3件目のトライアルがありそうです。
トライアルが迫っているから、というわけではないですが、原田國男さんの『裁判員裁判と量刑法』が目に止まって精読させていただきました。
原田さんといえば、東京高裁の元裁判官。高裁の弁護人ほどやりがいのない仕事はないといわれる中で原田さんの決まり文句は「弁護人の控訴趣意は認められない。しかしながら,職権をもって判断すると,原判決の量刑は現時点においては重きに失しているから破棄を免れない」として,なんだかんだいいまして弁護人の主張を多少なりとも酌んでくれるという点でした。
そんな原田さんは量刑法に関する専門家です。量刑法というのは研究者が少なく,事実上裁判員裁判が始まるまでは研究すらまともに行われてこなかったのではないかというのが実態ではないかと思います。そういう意味では院生などには是非、原田さんの『量刑判断の実際』などは呼んで欲しいと思いますし,私も控訴趣意に引用したりしております。しかし、量刑理論というのは裁判官もピンと来ないようで,ドイツの量刑理論を引いても分かっているのか、いないのか、という場面に出くわします。
新しい裁判員裁判の量刑の傾向は、全体として重いというのが弁護人をしている弁護士の感想ではないかと思いますが、氏の交通事故に関する新結果主義なる分析には正鵠を射るものがあるように感じました。
量刑の傾向としては,裁判官裁判とほぼ同様の量刑傾向を示している、そうです。
この書籍に励まされたのは以下の記述でした。
「さすが,弁護士は,人権そのものにかかわってくると銭金ではなく,本気で全力を尽くしてくれる。司法への信頼はこのような誰も注目しないような事件において実現されているのである・・・我が国司法の伝統的な被告人の改善更生こそが大切だという考え方が現れている」(原田國男『裁判員裁判と量刑法』(2011年、成文堂)206頁)
みなさまへ
私が幹事になっておりますチャレンジゲート中部主催のセミナーが開催されます。
◆日程:3月8日(金)
◆時間:セミナー第一部 18:30~19:30
セミナー第二部 19:40~20:40
セミナーの第2部は,「売りたいモノを売るな!」~事業計画書が書けない理由~です。
どきっとした方もおられるのではないでしょうか。
やっぱり売りたいものを売りたいのが,供給者心理。それに合わせて需要も伸びるとマーケティングの裏付けのない事業計画書を書いてしまうけどうまくいかない・・・
なんてことでお悩みの方はいらっしゃいませんか。
スタートアップの起業家が知らない、お客様の4区分と3つの数字。
実は、これを知らない限り事業計画書は書けません。
書いてはいけません。
◎自分が考えているビジネスでは売上があがらないのでは?
◎どう考えても想定している計画では事業が成り立たない。
事業計画書は,起業を考えている人だけではなく起業をされてまもない方,金融機関からの借入を検討しておく人,経営指針書などすごいものを作る前のステップとして関心のあるところですね。
講師は,曲尾悟志(有限会社ブラッシュアップ代表取締役)さんです。
事業計画書が書きたいけど書けない,とりあえずどうやって書いたら良いか知りたいという方は機会にされてください。
本日は、名古屋で最大の某税理士法人を訪問して参りました。
創業者が大変な勉強家で取扱分野が広がっていったというような経過があるのだそうです。
金融円滑化法の終了に伴う影響については、本日訪問させていただきました某税理士法人においては
「顧客が慌てているという印象はない」とのことでした。
リスケジューリングを受けているのは、全体の1割程度ですが、信金・信組については査定を厳しくするかどうかの動向が注目されます。
いろいろ示唆に富むお話を聴かせていただきましたが、高齢社会を迎えまして後継者への事業承継ということが関心を集めています。
これまでは、株価対策、相続税対策ということもあり、ばらまいてしまった株式を承継のために集めないといけないという作業をしないといけなくなります。
相続税は増税となりますが、事業承継税制は緩くすることによって相続によって事業承継に支障が出ることのない立法政策の配慮を求めたいところです。
セブンイレブン加盟店が、運営会社に対して、深夜営業の中止の申し入れをしてこれを拒否した行為が「優越的地位の濫用」(独占禁止法2条9項5号ハ)に該当するか、という挑戦的な裁判の判決が出されました。
結論としては、棄却されました。
コンビニ契約における24時間営業というのはオーナーのみなさんであれば分かると思いますが、負担が大きいものです。アルバイトを雇っているところもありますが逆に深夜にオーナーがレジをしているというお店もよくみかけます。
これまでも民法上の公序良俗違反などで争った例はあったのですが、独占禁止法の「優越的地位の濫用」を正面から持ち出した判例はこれが最初ではないかと思われます(東京地判平成23年12月22日判例集未登載)。
公正取引委員会は、加盟者が本部との取引が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても、これを受け入れざるを得ないような場合をいうとしています。
たしかに、セブンイレブンなら7時から11時までの営業というようには誰も思っていないでしょう。もっとも、地域によっては24時間営業というのは経済的合理性がない場合もあります。この判決は、利益・損益分担の公平性という観点が欠けていると考えられます。
深夜のわずかな売り上げによっても、本部は入金を得ることができることになるわけですが、お店をオープンしておくと縷々の経費がかかります。一番大きいのは人件費でしょう。夜間は強盗の心配から警察から2人以上の配置といわれることもあります。
運営会社の側が24時間営業のイメージという統一性を守りたいがために24時間営業にこだわるのであれば、相応の損失の負担もしなければ公平性に欠け、結果的には、受け入れざるを得ない状況にある、といえるのではないかと考えられます。運営側には東京地裁からすれば独占禁止法に違反するレベルではないにしても、代償措置の創設をして、利益・損益分担の公平性が保たれるようにするよう求めたいと思います。
愛知中小企業家同友会の景況調査報告(11月分)によれば,その判断は「弱含み」から「悪化」となることが分かりました。
建設業は比較的好調のようなですが,官需では太陽光システムの設置など補助金が出る関係の建設業が好調のようです。
民需で戸建ての需要はあるようですがローンの審査に通らない懸念が出てきているようです。
また,相変わらず職人不足で受注が難しかったり、受注価格が低すぎて受注できないという意見があるようです。
特に産業廃棄物関係では,到底受任に適さない不適正価格での自転車操業業者が多いと懸念する事も上がっています。
愛知県経済は,建設業は活発ですが,全体としてみると悪化の中にあるようです。
新政権の経済施策にも注意をしながら,外部環境に注意を払う必要がありそうです。
不動産関係からは,消費税が上がることによる顧客動向を気にする声もあるようです。
先般,宅建業者が媒介ではなく直接買い取りをする場合については,媒介契約では駄目な合理的根拠を示す必要があり,これがない場合は媒介契約にとどめる義務があるとの判決が出されました(福岡高裁平成23年10月17日)。
不動産売買に宅建業者のみなさんが関与している場合、媒介、買い取りが想定されるところではないかと思います。ですから、この判例は結構目が覚めたという方もおられるかもしれません。
ただ,宅建業法や判例では媒介手数料が高額にならないように制限をしてきているという経過があります。逆に,媒介手数料を制限しても買い取りが安い金額で行われキャピタルゲインを得られるということになると媒介手数料に対する規制が無意味になってしまうという趣旨と考えられます。
この判例は,媒介では駄目である合理的根拠を求めています。
もっとも,この判例を読むと「売買代金1500万円の4割差益(600万円)を得ていること」が重視されているようです。
宅建業者としては,契約成立までのスピード感,履行の確実性,安心感などで合理的根拠を基礎付けようとしましたが,600万円のキャピタルゲインを得るための合理的根拠としては認められなかったといえます。
本件のように宅建業者が自分で買い取りをして,そのキャピタルゲインを得た場合についてその当否が問題とされたのは,公刊判例では1件しかありませんでした。
その中で,合理的根拠が必要という新たな視点を示して,その検討の方法の道筋を示していることは宅建業者のみなさんの執務の参考になると思われます。
もっとも,判断の過程は,宅建業者の言い分を,ひとつひとつ論破していくという構成がとられていますので,その判断基準が明確に示されているとはいえないと思われます。
この件では,宅建業者側に約527万円の支払が命じられています。
購入当時69歳と71歳の夫婦に対して,証券会社が販売した投資商品の説明義務違反を認めた判決が出されました。
このケースでは適合性原則違反,要するに商品の内容にも問題があると指摘されています。
商品の内容は,豪ドル建日経平均連動債でした。期限が10年なのですが,基準日に日経平均株価終値が103%以上になれば早期償還されます。
他方、観測期間中に一度でも当初の56%以下になれば以後は下落率に応じた損失が発生する仕組みでした。
さらに,当初の3ヶ月を越えますと日経平均株価が当初の80パーセント以上かどうかで利率が大きく変わるというものでした。
このように,仕組みが複雑でいて,必ずしも理解が簡単ではなく高度なリスクも存在する場合については,購入者の投資判断の能力も考慮するべきことを示唆したといえます。
ここでは,担当者から一応の説明はあったものの、担当者が原告らの属性や投資意向を正しく認識していませんでした。また,顧客保護のための社内体制の不備を指摘されており適合性原則違反だけではなく,説明義務違反を認めた事例として注目されます(大阪地判平成24年12月3日)。
従業員の退職にまつわるトラブルで比較的多いのが,製品の製造過程についてのマニュアルや顧客名簿の持ち出しです。
不正競争防止法の営業秘密の保護については範囲が狭く、
「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」とされています。
加えて図利加害目的まで要求されるなど,その従業員の不当な意図という内心の立証をしなくてはいけませんので,困難が伴う面があります。
特に,他の会社にも類似のノウハウが存在するものは営業秘密にはなりませんし,顧客名簿の持ち出しも営業秘密ではありません。
名簿を持ち出した場合は窃盗罪で刑事告訴するという方法もありますがデータで盗まれるとなかなか対応が難しい面があります。
そこで,不正競争防止法に頼らずに労働契約による守秘義務を設定しておくことが重要となります。これも包括的すぎても公序良俗違反となり法律上の効果が否定されることもあります。
裁判例では,顧客名簿に関しては,誓約書により期間の定めのない守秘義務を設定したケースでは,秘密・情報の性質・範囲,価値・労働者の退職前の地位に照らして合理性が認められる場合は,公序良俗違反にならないとしています。
この場合は労働契約による守秘義務の設定の有効性が争われることになります。これも裁判例に照らした設定にしておく必要があります。例えば,商品取引所の上場商品の売買を含む会社の従業員が同業他社への移籍に際して顧客情報を無断で持ち出したことにつき,就業規則及び同内容の守秘義務の内容を明確に列挙していることから有効と判断した例があります(アイメックス事件)。
先月が自分のチームの例会の主催側ということで,二ヶ月連続での例会参加となりました。
報告されたのは,特殊印刷製造業、印刷、シール関連などが業務内容の方でした。
例会は勉強会という位置づけをしているので関心があるテーマには参加をしているようにしていますが、例会のテーマは「伝え、そして実践」というものでした。
現在の経済学の主流というのは、経営戦略をどのように構築するかというコンテンツの研究にシフトしてしまっています。もっとも、昔は、PDCAサイクルのPが先か、Dが先かというような神学論争をしているうちに手続的な観点からのアプローチは廃れていったというのが、現在の経営学の実情といえるのではないでしょうか。
私の事務所の場合、計画があって実践という発想が強いようですが、時代の潮流に乗り遅れている憾みがあるかな、と感じています。私は考えるよりも即実践、そこからDCPAサイクルになってしまっているかもしれません。Googleのように、まず実践というのは若々しい企業が多いと思います。
私が、中小企業の法律サポーターを始めたのも、「考えつつもなお実践」で,「とり急ぎ事業を始めた」方を応援するためです。
報告では、中小企業としてのビジョンとして,「変革と挑戦」~市場創造と人材育成を掲げておられました。
今「やる事を違った方法でやるのではなく,やる事自体を変えること」、との指摘があったように思いました。
根本的な指摘で示唆に富むものでした。
昨日,中小企業家同友会の室会の女性会員さんの報告がありました。
広告宣伝用の可愛いポストカードを作って配ります。街頭でチラシを配るよりも効果的なそうです。
可愛くつくってあるのでイメージを浸透する効果もあるそうです。
彼女、30代になってからの起業で、その起業のあり方もみなさんも聴いてみるとおもしろいです。
さて,起業で3年目を越えて安定期に入ってきたのか,従業員さんの待遇にも気を使うようになったということのようです。
起業した会社の「成長」のお話をうかがうのは興味深く思います。
起業する企業は1年間で大半がつぶれてしまうといわれています。
私も起業のアドバイザーとして起業を応援しています。
それだけに、彼女の成功の秘訣を聴けたと思います。
繰り返すのは、「縁と運とタイミング」が大事ということでした。
なお、どのようなお仕事を任せるかにもよるのですが「記事の取材・編集の業務」「デザイナーの業務」は,みなし労働時間制の対象となる裁量労働となります。
これは、労使協定によって、仕事のすすめ方を労働者の裁量に委ねることにした場合、その裁量労働に従事する労働者については、協定で定める時間労働したものとみなすことができるというものです。
例えば、1日の仕事は9時間かかるかな、とすると実際の労働時間にかかわらず、1日につき1時間の時間外労働とされて割増賃金を支払うということになるようです。
彼女の雇い入れている人たちは「記事の取材・編集の業務」に当たる可能性があるので,まだ組織化が進んでいませんので良いとは思いますが、法制度が整備されていますから利用の検討がいいかもしれません。