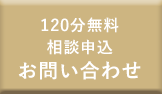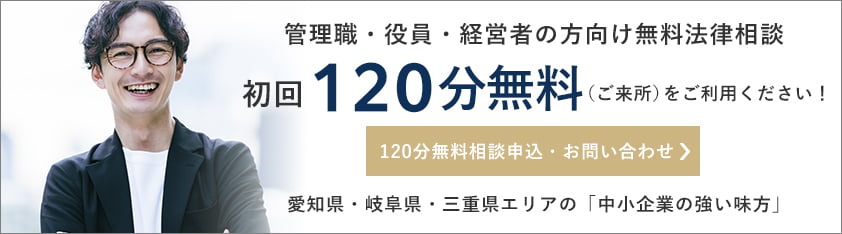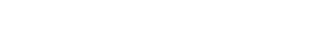お役立ちコラム
医療過誤や医療ミスが起こった場合、被害者の方は原状回復をお求めになります。
そして、原状回復が適わない場合は説明と適切な賠償が医療訴訟の実務の原則と考えられます。
当事務所は、医療ADRに関心があり、医療問題の当事者の自主的解決の代理を目指し、所長弁護士は紛争解決センターの運営委員をしています。
和解の内容については、予防接種法が施行された1948年7月から1988年1月までに6歳以下で、B型肝炎ウィルスに感染しており、一定の条件を満たす場合に、死亡から無症状の持続感染者まで病態に応じて50万円から3600万円を支払うというものです。
一定の条件とは、B型肝炎ウィルスに6ヶ月以上持続感染している、満7歳になるまで集団予防接種を受けた、1948年7月から88年1月までに6歳以下であること、母子感染ではないこと(例外あり)、他の感染源がないというもので、原則として給付金を得るには訴訟を提起する必要があります。しかし、弁護士費用の援助もできますから、実質的な弁護士費用は実質4パーセントです。実費はお預かりしますが、着手金は無料です。
B型肝炎訴訟は給付金を得るために訴訟を提起する必要がありますので、当事務所では、自分の親族が脳神経外科にかかったことがある経験、父親の死亡といった体験から、原状回復のための給付金訴訟のお手伝いをさせていただくことが当事務所の理念に沿うものと考え、積極的取り組みを行うことにいたしました。B型肝炎訴訟問題でお悩みの方は当事務所に是非ご相談ください。なお、当事務所は共産党系の事務所ではありませんので、脱原発のデモ行進に参加を強要されたり、ビラをもらって不愉快な想いをされるということはない理念を掲げた公平な法律事務所でございます。どうぞお気軽にご相談ください。
また、当事務所では医療過誤被害者ADR申立支援を行っています。現在、地方公共団地に苦情窓口が設置されていますが、医療裁判までは難しいかもしれないと悩まれている方もいるかもしれません。健康を害された場合は原状回復が必要となります。
しかし、医療ADR(愛知県弁護士会紛争解決センター)では、申立の法律相談を行っていません。そこで、申立サポートを当事務所で行っています。愛知県弁護士会の医療ADRには3つの特徴があります。まず、裁判と異なり話し合いが可能になること、専門委員という医師がおり仲裁人に協働して医療知識を提供すること、医療機関の応諾率が90パーセントを超えており、専門性の高いADRといえます。年間46件ほどの申立がありますが、これは名古屋地裁医療集中部に係属する事件数と変わらない件数といわれております。また、少額の事案についても比較的解決に向きやすいというメリットもあります。
医療ADRは、合理的な医療の悩み・健康被害がある場合の原状回復、説明責任の履行、医療機関側も合理的な医療の説明責任の履行の場としても活用されており、第三者医師である専門委員からの共助が得られる場合もあり得ます。
主には、内科、外科、整形外科、産婦人科、歯科、美容整形について取扱があります。
医療ADRは弁護士会が運営する患者様にも医療機関側にも公平かつ中立な紛争解決機関となっております。
ご利用をお考えの方は当事務所にご相談ください。
アドレスは、以下となっております。
http://www.horitsu-supporter.jp/adr
サッカーの日本代表には頑張ってもらいたいですね!
さて、税務調査というのは、いつやってくるのでしょうか。
税務調査先の選定は、業種・規模・業績・過去の調査実績などの要素に基づいて行われているようです。
近傍地域との比較も要素になっているという説もあります。
ですから、いつころ調査に入るかということの予想は難しいといえます。
従業員10名の会社では6年~7年くらい、売上や経費がほぼ一定の会社は、あまり税務調査のないという傾向もあります。
さらに、なんといっても、税務調査の多くは、赤字の会社よりも黒字の会社の方が多いということです。赤字会社ですと、かえって、還付という事態になってしまいますからね。
赤字会社でも全く税務調査がないというわけではなく、実質的に節税目的とみられる会社などは注意が必要のように思われます。
予備校には、入学したもののやっぱり行けなくなってしまったというケース、結構ありますよね。
予備校や塾を経営している人もいると思うのですが、大分地方裁判所平成26年4月14日は、解除後の期間に対応する授業料の全額を返還しないことを定めた本不返還条項は、平均的損害を超えるものとして、消費者契約法9条1号に該当するものとして、平均的な損害を超える部分が無効となるとの判断が示されました。
大学の入学金をめぐる判例はあるところですが、予備校について中途退学は認められない、というのがこれまでの常識だったように思いますが、大分地裁は、契約書ひな形の破棄を命じています。
全く返還しないという条項となっている場合は、契約書の見直しが必要となるでしょう。
毎月分配型投資信託の販売勧誘時、分配金に、元本の一部を払い戻す性格を有する特別分配金が含まれている等の説明がなかった場合は、どうなるのでしょうか。
この点、パンフレットにも記載がない場合については、販売した銀行及び投資信託組成者である投資信託会社の説明義務違反による共同不法行為が認められ、一定の賠償性帰任が認められたものです。
銀行と投資信託会社の説明義務違反を認めた裁判例としてめずらしいものと思われます(東京地裁平成26年3月11日)。
インターネット上のサイトの記載の一部について引用したいという相談を受けることがあります。
原則的には、無機質で何回建て、色は白などの事実であれば創作性はないといえると思います。
もっとも、創作性があるものであれば、その権利は記事を書いた人、特にサイトであればサイト自体が著作物となりますので、無断で記事を引用すれば「引用」の要件を該当しない限り著作権侵害となります。
文章にかかわらず、記事自体に筆者の個性がなく、また、表現がありふれたものであれば、創作性がないので著作物となりません。
書き込まれた記事には、創意工夫がないもの、単なる事実の羅列、筆者の個性が認められないもの-を除いて、思想または感情を創作的に表現していると判断される可能性が高いと考えられます(東京高判平成14年10月19日)。
なかなか「引用」の要件を満たすのも商用サイトの場合は難しいでしょうから、他のサイトの記事を引用・転載する場合は注意が著作権を侵害しないように注意が必要です。
案件はオーソドックスなものでしたが、口外禁止条項もございますので、詳しくはお話することができません。
解雇、整理解雇、退職勧奨でお悩みの経営者でトラブルが顕在化されていて困っている方は、是非ヒラソルにご相談ください。
債権者は嘘をつく。
なんだ、そんなわかりきったこと、ということのように思うかもしれませんが、最初は、嘘をついているようにはみえずナチュラルに嘘をつくのが、債務者の特徴といえるかもしれません。
おそらくは、長年の事業で培われてきたものなのか、と思うときがあります。回収の話しをすれば、「1ヶ月後においしい入金話しが」と真面目に話し出します。
債務者は、自分にとって都合の悪いことはいいません。いわないだけであれば良いのですが、積極的に嘘をつかれるというのが一番困るように思います。
債務者の嘘がナチュラルなのは、債権者を安心させるためなので、自己保身もあるものの、相手を安心させるという目的があるからかもしれません。
現在では、「勝負の勘」で、いろいろ大変・・・といわれても、これが債権回収の場であると割り切って、基本的には、いっていることの8割引きくらいで話しを聴くと意外感がありません。
よくあるパターンが大きな取引が決まり・・・というものですが、裏付け資料の提出がない限りは信用してはいけないですし、その代金を真っ先に回収することを考える必要があります。
債権回収は、時間が経過すればそれに比例して回収率が低下していってしまいます。
しかし、時間が経過すれば、資産処分を始めたり、金融機関へのリスケを行い始めたりして、何よりも支払う「意欲」、つまり踏み倒せばいいじゃん、という感情が出てきます。
そこで、債務者を取り巻く情報と債務者の信用情報の収集には全力を挙げましょう。
債権回収は倒産一歩手前の危機的状況こそ勝負の分かれ道となります。
この場合は支払を待つという選択肢はありません。他の債権者に先を越されてしまうだけになってしまいます。
とにもかくにも怪しい噂を聞いたら、債務者に会いに行くことです。顧問弁護士として同行したこともありますが、債務者の言い分を聞きながら債権回収の方策を考えることになります。
債権者、しかも顧問弁護士も連れてきているということになると、債権者の心理としては拒否しづらくなります。
そして、この場合でも倒産の危機があるかを見極めながら、信用情報を得るように努めることが大事であるといえます。
さて、日本には多くの中小企業がありますが、多くの中小企業は税法上の有利選択のために法人を設立しています。
結構個人商店にみえても法人になっているケースがあります。
歴史的経過としては、昔は個人事業主であっても「みなし法人課税制度」というものがありました。これによると個人事業主も給与所得控除がありました。
こうして経費と給与所得者控除の二重取りを認めていましたが、平成4年に「みなし法人課税制度」は廃止されましたので、これを機会に法人設立が増えたように思います。
当たり前ですが、このようなインテンションですと、経営者は、年間の利益を予想して、それとピッタリの役員報酬を設定するということをすることになります。
なぜなら、法人に利益を残してしまうと、法人税が課税されること、内部留保についても将来清算所得に課税が生じるからです。
また、役員報酬を家族に分散することにより累進課税による適用課税の税率アップを防ぐことができるということがあります。
理論的にいえば、個人事業の場合、所得税、住民税、事業税がかかります。税負担は約4割といわれています。
そこで配偶者に給料を支払うことになります。専従者給与と呼ばれています。専従者給与を支払う理由は、所得分散による税率を抑えること、給与所得控除の理由の2つです。
個人事業主の人は給与所得者控除はありません。しかし、妻は給与所得者控除を利用できます。また、所得を分散して税率を軽減するというのは分かりやすいところですね!
これを推し進めると、法人設立となります。なぜなら、法人を設立すると、所得を3つに分けることができます。会社、自分、配偶者という形です。
3つに分ければ、税率軽減も有利なようにできる、ということに加えて、経営者自身も給与所得者控除が利用できるようになるのです。
こうして、課税される価格が低くなりますので本人の所得税が安くなりますし、事業税もいらなくなりますので、結構な税金が安くなります。
実は、街の八百屋さんや食堂もなぜか法人になっているのは、税法上の理由が大きいですのですが、せいぜい本人の税金+事業税で、3000万円の所得の場合約170万円程度が節税になります。
もっとも、これからは、あべこべの現象が起こりますので、会社の設立自体は減らないでしょうが、すべてを役員報酬に回すメリットはなくなりつつあります。
私の関与した会社でも、利益が出ると、賞与としてばらまいてしまい内部留保ゼロをモットーにする会社がありました。
しかし、法人税の税率は中小企業の場合、800万円を基準に別れています。これ以外の税金を加えた実効税率は概ね800万円以下は25パーセント、それ以上は35パーセントです。
ところで、所得税の方は他方で増税となっています。復興特別税が25年間も上乗せされます。
また、役員の給与所得者控除についていえば、245万円が限度額となりましたので、1500万円以上の所得の場合、それほど給与所得者控除のメリットがなくなったということになります。
さらに、今後、給与所得者控除は段階的に引き下げられ、2017年のMAXは、220万円になります。
したがって、役員報酬が高いと所得税も高くなる、ということになりますから、これまでの会社の利益をゼロにして、なるべく役員報酬で受け取るという時代は、だんだん終わっていくと思われます。
むしろ、会社内部に内部留保を残しておく、ということが中小企業にとってもある程度の流れ(といってもメジャーになるとは思えませんが)になると思われます。
今後は、法人なりした企業が「個人なり」するか、はたまた所有と経営がある程度分離した中堅企業化していくかに論理的に分かれていくと考えられます。
会場の設営スタッフとして、落語会を主催している場合、居眠りをしている人を追い出してもよいでしょうか。
一般的な対応としてはほかっておく、というケースが多いかと思いますが、いびきがうるさい場合など、興行の支障になることもあります。
そういう筆者も結構・・・、(い)オレンジレンジのライブで、後部座席のためカメラに入ってしまうから退去して欲しいといわれた(これは結構どうかな、と当時は思いました。)、(ろ)パリでクラシックのコンサートにいったが、全然知らない曲目のときに寝てしまった-という経験があり、客の立場からも人ごとではありません(笑)。
裁判例では、退出させる場合、同人の不利益を考慮する必要があり、退出しなければ演目の続行が困難、主催者側の言動が社会通念上相当と認められることが必要とされています。
結論においては、損害賠償請求は、落語家の方がモチベーションが下がってしまうといった事情があったこと、反省の態度がない、中断をした、との関係で不法行為ではないと判断されました。
こうした観点からすると、少なくともオレンジレンジの件では、観客の側に入場料を払ってコンサートを堪能したいという意思・姿勢もあったところ、後部座席であるためカメラに入ってしまうから退去して欲しいというのは、かかるカメラがライブカメラとはいえず、演目の続行にも支障がないので、事態の進行によっても演目が中止になることもなく、原因が専ら主催者側にある場合において、より制限的でない他の選びうる手段、つまり空席や関係者席に誘導するなどの措置を講じる信義則上の義務があったのではないかな、と思うところです。そのときのスタッフは「カネを返すから出て行ってくれ」ということでしたが、こういう対応はサービス業としてはあり得ないでしょうし、裁判例に照らしても名誉を毀損し不法行為を構成する可能性が高いと思います。こうした主催者本位の行動は、ひいてはアーティストの評判にも関わるでしょう。
他方、クラシックのコンサートは、親切な人が起こしてくれましたが、とてもマイナーな曲でしたが、なんとか、耐え抜いて聴いて、お目当ての曲を堪能することができました。