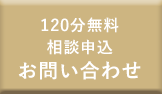お役立ちコラム
名古屋の中小企業の法律サポーターのページです。
請負契約の場合、瑕疵があれば、請負人に修理をするように請求をすることができるものと考えられています。
この点、雨漏り、水漏れなどがあれば、通常備えている品質や性能を欠いているので瑕疵があるといえるかもしれません。
問題は、こうした建築紛争はすぐには表面化せず、台風などの被害で表面化することもあります。
修理を請求できる期間は、木造建築の場合は、原則として、引渡しから5年です。
コンクリート造など強固建物の場合は10年となっています。
そして、ここでのポイントは、契約書で修理請求期間を短くできることです。
例えば、民間連合協定工事請負契約約款では引渡しから1年から2年とされています。
もっとも住宅品質確保法という救済法が立法されました。
これによりますと構造耐力上主要な部分又は雨水の進入を防止する部分に瑕疵がある場合、
引き渡しから10年間請求可能と救済措置がとられています。これは強行法規です。
したがって、雨漏りの場合については住宅品質確保法によって、雨漏りの修理を要求される可能性があるといえるでしょう。
ポイントは、
構造耐力上主要な部分か
雨水の進入を防止する部分の瑕疵か
という法律要件になっています。
いつも名古屋駅ヒラソル法律事務所を御愛顧いただきまして心より御礼申し上げます。
暑い日が名古屋では続いておりますが、ご身体ご自愛ください。
さて、名古屋駅ヒラソル法律事務所では、13日、14日はお盆態勢とさせていただきます。電話がつながらない場合は、少し時間を置いてからおかけ直しください。
15日及び16日は電話対応はお休みとさせていただきます。
したがいまして、弁護士が所内などで対応できる場合のみ応対をさせていただきます。また弁護士対応のため留守番テープが流れないなどの不都合が生じることもあるかと思いますが、ご了承ください。
もっとも、既存のお客様は大変恐縮ですが記録担当の法務担当事務局が、お休みをいただきます関係上、進捗などのお問い合わせは、7日まで、あるいは17日以降にお問い合わせいただきますと幸いに存じます。
中日新聞平成27年7月9日によれば、憲法学者の9割が、安保法案を違憲といっているという。
しかし、一部でも違憲であれば、という意味ですべてが9割というわけではないと思われる。
たしかに、立命館大学の憲法学者は市川正人先生も含めて違憲のようだ。松井茂記教授などはどのように考えるのか、少し気になるところだ。
違憲の理由を分類すると、集団的自衛権の行使容認が憲法9条に違反していると考えている学者が多いようだ。
しかし、安保法制は法律が多く、何が違憲で、何が違憲かもしれないけど常識に合致しているのかもよく分からない。
集団的自衛権というのは「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」という】定義のようだ。従来、集団的自衛権というのは、同盟国が攻撃されたら一緒に戦う権利と定義されていたので、中日新聞の報道はこうした従前の定義から違憲と判断した学者が多いのではないかと考えられる。
たしかに、憲法9条1項は国権の発動たる戦争は行わないのであるが、正当防衛的、反射的な自衛権までは放棄されていると解することはできない。また、2項は陸、海、空軍はこれを保持しないとあるが、自衛隊は実力行使部隊なのであって、警察力であるから軍隊にあたらない。こうした理論的視座及び日本国憲法が13条以下で基本的人権を保障していることからすると、日本に急迫の危険があり、幸福追求に関する権利が根底から覆されるような明白な事態があるのであれば、その実力行使の範囲を日本国内にとどめる根拠はないというべきで、いってみれば「自衛権」の範疇で、海外で実力行使をすることが憲法9条1項2項に反すると解することはできない。したがって、存立基盤事態に対する実力行使自体は合憲といわざるを得ないだろう。問題は、「あてはめ」であり、中東での機雷除去が存立基盤事態といえば、たしかに機雷が除去されることによりオイルの輸入などがスムースに進むという意味での合理性はあるかもしれない。しかし、仮にオイルの輸入がスムースにいかなくなることが、幸福追求に関する権利が根底から覆されることが明白なはずはない。そういう意味では、あてはめの間違い、恣意的な運用ができない立法政策が望まれる。
もっとも、存立基盤事態よりも問題なのは、重要影響事態である。要するに存立基盤事態との対比で大したことない場合の話しをしているのだな、と分かります。重要影響事態は、ざっくりいえばイラク特措法を恒久法にするという印象のもので、地理的制約がなく、日本の平和と安全に重要な影響を与える国際紛争と判断すれば、自衛隊が世界のどこでも他国軍を支援できる、のだそうだ。イラク法にあった非戦闘地域という概念もなく、戦闘地域で他国軍の支援をしてもよいということになるようです。しかし、個人的に、これはどうなのだろうと思ってしまいます。
日本の自衛隊が直接実力行使をしないからといって、他国を支援していたら共犯、共同行為とみられるでしょう。刑法理論では共謀共同正犯理論があり、一部でも重要な役割を果たしていたらそれは「武力行使」になるというのは、イラク法に関する名古屋高裁の違憲判決です。ただ、捜索救助活動と書いてあったり、他国軍の支援と書いてあったり、重要影響事態は外延がはっきりしておらず、曖昧であるか故に無効の法理の適用を受けるほどではないか、と考えられます。しかし、重要影響事態と存立基盤事態の対比はどの程度なのでしょう。正直為替の変動すら「影響」といえます。いくらなんでも、日本の安全に影響という定義は抽象的すぎるのではないかと思われます。
そのほか、自衛隊法改正では、自衛隊の防護が可能になったり、テロ被害に遭った在外邦人の救出もできるようになるのだそうです。
以上をみると、集団的自衛権をいわれる存立基盤事態はむしろ合憲と評価される一方で、重要影響事態や自衛隊法改正による米軍護衛が可能になる、ということの方が、他国の軍隊と有機的に相互に補充し合って結果発生を助長するのですから、他国軍隊との結びつきという名古屋高裁の判断が軽視されすぎているのではないか、と思います。
結論からいえば、私見も、海外で起きた紛争が日本の安全に影響する場合、米軍や他国軍を支援という中日新聞報道を基礎にすると、重要影響事態安全確保法は、我が国の幸福追求権が根底から覆されるなどの事態ではないので、日本国内のみで自衛隊は活動すれば足りるのであって、他国に出国する論拠を「影響がある」といってもどのレヴェルでいうのかを明らかにしない限り、定型的な立法による「影響」という用語からすれば、例えば戦争が海外で起きて日本人が巻き込まれそうというだけでも影響は受けるので、あらゆる戦争の後方支援が必要で、それが日本の幸福追求と何ら関係なくてもできる、国際私法のパワーゲームの材料にするかのようで、憲法法制史的にも是認できないように思われます。そういう意味で、イラク特措法が建て付けが良かった分、今回の飛躍ぶりがすごいな、という印象を受けます。
先般のアメリカ連邦最高裁が、同性婚を憲法上の権利を認めたことは、その判決文をみると保守派対リベラルの対立なのだが、歴史は違う形で繰り返しているようだ。
アメリカでは、司法積極主義と司法消極主義の対立が昔からあった。要するに難しい問題は、立法府や行政府に任せて自分たちは「評論家」に徹しようというわけだ。
昔、少年部の裁判官から「自分は評論家だ。だが評論家ばかり増えても仕方がない」といわれたことがあったが、その裁判官は少なくともそういう司法消極主義に身を委ねているときであった。
実は、アメリカの憲法訴訟論では、憲法問題を連邦最高裁が判断するべきではない、という憲法判断回避のルールが存在している。いわゆるブランダイス・ルールが典型的である。
ブランダイス判事の補足意見は「裁判所は憲法問題が提起されても、もし事件を処理することができる他の理由が存在する場合には、その憲法問題に判断を下さない」というわけだ。
実は、同性婚に関する反対意見においても同じような意見が述べられた。
「憲法には同性婚をする権利について明記されていないが、多数意見は修正第14条のデュー・プロセス条項の「自由」がこの権利があるという。合衆国はすべての人間が自由への不可侵な権利をもつという理念のもとで創られたが、自由は多義的な意味をもつ概念でもある。伝統的リベラル派にとっては、自由は現在政府によって規制される経済的な権利を含むかもしれない。社会民主主義者にとっては、それは各種の政府による給付を受ける権利を含むかもしれない。本日の多数意見にとっては、ポストモダンのようだ。選挙によって選ばれていない5人の最高裁判事が、みずからの自由に関する見解をすべてのアメリカ国民に押し付けることができないよう、最高裁判例ではデュー・ プロセス条項の「自由」が「この国の歴史と伝統に深く根ざした」権利のみを保障すると理解すべき、とされている。そして、同性婚の権利がこのような歴史と伝統に深く根ざした権利とまではいえない」
そもそも、今回の反対意見では、では憲法に記載のないプライバシー権や良好な環境を享受できる権利なども「歴史と伝統に深く根差した」といえるか、あまりに原状変更に否定的であることが分かります。
実は、日本も原発訴訟をめぐって司法積極主義と司法消極主義が分かれているというか、司法消極主義が優勢といえるでしょう。
近時は仮処分を通じて、福井地裁と鹿児島地裁の見解が対立しているようです。
しかしながら、アメリカ連邦最高裁は、このように司法の役割を論じます。たしかに違憲審査制の憲法保障機能を害するところが出てくるでしょう。
私見においても、裁判所は事件の重大性や違憲性の程度、及ぼす影響、事件で問題にされている権利の性質をベースラインに、十分理由がある場合は、憲法判断に踏み切ることが妥当だ、と考えられます。
連邦最高裁は、「不正義というのはえてして、同時代に生きる人間にはみえないことがある。権利章典と修正第14条を起草した先人たちは、自分たちがすべての面において「自由(liberty)」が意味することを理解しているとは考えず、将来の世代に対して、時代の変化によって変わりうる「自由(liberty)」を憲法上の権利として保障できる仕組みを残した。新たな洞察によって、憲法上の中核的な保障とその時代の法体系の間に齟齬があることが明らかになったときには、自由が憲法上の権利として保障されなければんらない。」との立場です。
日本の最高裁では、事実認定が問題であるとして、一部無罪を言い渡すべきと主張した判事2名と最高裁判所は法令解釈をする場とする判事3名が対立し、2対3で上告棄却となりました。
しかし、刑事裁判の場合は、無辜の不処罰という大義名分があるはずで、実際、最高裁が冤罪を見抜いて破棄差し戻した裁判も過去にありました。
しかし、上記連邦最高裁の意見には、少し思うものがあります。たしかにロールズがいうように人間は、不正義を感じるその回復の過程に正義を感じる、と論じます。そして、時代によって、みなが感じ得る不正義は異なるはずです。特に代表民主制の過程で代表者を送り込むことができない少数派グループなどは、彼らが感じる不正義を得てして多くの多数派は感じ取ることができないと考えられます。
さて、原発問題については、えてしてそこでの不正義は原発の傍に住まない人には見えにくい。それを不正義とみて是正する必要があるのか、国民的評価も割れるように思われます。
非嫡出子違憲訴訟で3対2で合憲とされた裁判例で泉判事は、「嫡出でない子が被る平等原則,個人としての尊重,個人の尊厳という憲法理念にかかわる犠牲は重大であり,本件規定にこの犠牲を正当化する程の強い合理性を見いだすことは困難である。本件規定は,憲法14条1項に違反するといわざるを得ない。本件が提起するような問題は,立法作用によって解決されることが望ましいことはいうまでもない。しかし,多数決原理の民主制の過程において,本件のような少数グループは代表を得ることが困難な立場にあり,司法による救済が求められていると考える。」と司法積極主義の意義を説いているものと考えられます。
原発訴訟については、どのように考えるべきなのか、なやましいところといえるでしょうが、司法消極説が多数を占めていることで、「合憲評論家」になるのでしょうか。
福井地裁の大飯原発訴訟でみられる判決文は解釈の指針、ベースラインまで示しています。
「原子力発電所の稼働は、法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである」「人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている」と指摘しています。
借地借家法28条において、正当事由のベースラインとされるのは、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情となります。
それ以外は補完的要素となると考えられます。
賃貸人としては、収益物件であることが多く自己使用の必要性に乏しいことが多く、大家の事情としては、主に建替の必要性と立退料の提供となるように思われます。
結局、「老朽化といっても幅があるので、敷地の有効利用の観点と結びついている」ケースが多いといわれていますが、他方、「純粋に経済的な効用の喪失のみを理由とする建替を理由として正当事由を認定させるのは難しい」という指摘もあります。そこで補完要素としての正当事由と流れることが多いと考えられます。立退料は、ベースラインからすれば、補完的なものですが「かなり重要な一要素」と判断されています。
そこで正当事由の論拠となる立退料の内容については「建物明渡しに伴う当事者双方の利害得失を調整するため、建物明渡しによって被る借家人の損失を公平の見地から相当な限度で補償するもの」とされています。具体的には移転費用、借家人が建物利用によって事実上得ていた経済的利益、営業上の損失、地域社会において築いた社会的地位や人間的結びつきの喪失等が挙げられています。もっとも、借家人も事業者である場合は、営業権に比例するものまで賠償する必要性があるのか、隣地で端的に事業所を探せばよいだけではないのか、といった疑問もあります。
バブル期以降では、高額の立退料が提供されることはなくなり、正当事由訴訟も減少することになったといわれています。要するに背景としては、バブル期は、供給が逼迫して大家有利の状況があったものの、かえってバブル崩壊後は、供給過剰になり賃料の下落を招くなど借家人有利という社会的実態があるように思われます。そこで、移転実費と移転前後の賃料の差額を基礎に算定した事例などもあります(東京高判平成12年3月23日判タ1037号226頁)。
今回は、最判平成27年4月9日を紹介したいと思います。
11歳の少年が、サッカーをしていたところ、ボールが道路上に進入しました。そして85歳の高齢者が転倒し誤嚥性肺炎により死亡したものです。
形成外科的見地から誤嚥性肺炎になるのかどうかも争いのポイントになるのではないかと思います。
そこで両親の責任が追及されましたが、これを認めた大阪高判平成24年6月7日を破棄し、請求を棄却する判決を言い渡しました。
民法714条については、広範囲に及ぶ監督義務の内容があることに照らして、その免責事由の立証に成功することは極めて困難であるとされています。
同条については、免責を認めた裁判例は存在しませんでした。
本件についてみると、ゴールに向かってボールを蹴らないよう指導しない限り事故を防ぐことができなかったことに照らすと、親権者が負担するべき監督義務の内容の範疇を超えるものと考えられます。小さな子どもについては、生活全般についてその身上を監護し教育すべき義務としての一般的監督義務、当該事故の態様・性質に即したものとして、危険発生の予見可能性がある状況下で権利侵害の結果を回避するために必要とされる行為をすべき義務の両方の観点からの検討が必要とされています。
この判例は、民法714条1項の監督義務者の責任について免責を最高裁として初めて認めた裁判例として実務上参考になると思われます。
弁護士会の消費者相談研修会に参加してきました。
主に電話機リースなどで訴えられた場合、事業者としてどのように回答するのか、という観点から検討されました。
もっとも、消費者を意識した検討もあるので特商法の訪問販売該当性、消費者性の該当性について検討が加えられました。
この点、特商法の2条1項に規定する訪問販売該当性、消費者該当性のハードルは高いと思われますが、特商法の適用を認めた名古屋高裁なども報告されました。
報告によると、電話機リースについては、訪問販売に当たり得るという通達が出されているとのことです(経済産業省平成17年12月6日通達との報告)。
そして消費者該当性は困難性を極めることになりますが「事業実態がほとんどない零細事業者の場合は適用される可能性が高い」とのことですが、個人事業主を念頭においており法人での契約の場合は厳しいのではないか、との見立てとなり、詐欺取消し、詐欺の不法行為などの討議をしました。若手弁護士の難しいところを狙うような内容をベースラインとされました。
もっとも、ある弁護士がいったように、早く詐欺で取り消して物を送り、継続性を断ち切ることが優先という趣旨があったと受け止めましたが、リースの場合、明示の意思表示がない限りどんどん契約は更新されてしまいますので、既払いはともかく将来分の発生を防ぐというのが得策との意見も出て、比較的活発な討議が行われました。
聴き取りポイントとしては、
・契約締結の経過
・契約書の署名押印
・契約締結時の書面等
・光回線の契約なのにリース契約の対象が拡げられていることを知っていたか
・参加者
・電話機の使用状況
・決算書
などが指摘され、今後の執務の参考となりました。
愛知県弁護士会では、医療ADR、つまり医療関係の申立が大きくなっております。
そうしたご縁で、ある会議に参加して参りました。
各自治体での悩み、議題についての討議が行われました。
愛知県弁護士会といたしましても、紛争解決センターでの仲裁・斡旋がすることができるということ、実情について報告をさせていただきました。
今期は、税理士の浅野さんを中心とするグループに配属となり、弁護士・税理士・司法書士・公認会計士と士業方と会社経営の実業方が半々のおもしろいグループとなりました。
それぞれ観点が異なりますが、昨日報告されていました方は公認会計士さんでしたが、浅野グループは優しいグループなので、事業ドメインなどに曖昧な点がありましたが、指摘はでずこれから頑張っていこうという未来志向の報告になりました。
たしかに、優秀な経営者の方とお会いすると税務会計ではなくて、部門別のいわばアメーバ型の会計で、税務の加算・減算をなくして、かつ、現実の限界利益や営業利益が分かるようにしてある方がおり、私も通知税理士業を行っていますが、「会計学」という観点からの監査というのも、コンサルティングとして実益があるのではないか、と考えられました。京セラでも独自の減価償却期間を設定しなるべく税務会計ではなく実際の会計、つまり経営のコントロールタワーにするということが重要という叙述もあります。
また、建築方向の方で、巻き込み力が強い人がいるのですが、社員旅行で南西諸島に行くのだそうで、そうした福利厚生も、社員を止めさせない一つの経験的なものなんだな、と社員さんを大事にされている気持ちが伝わってきました。なかなか建築というのは裏方で、一般のお休みや閑散期が繁忙になるなどして、いろいろ工夫なされていました。
当事務所も、同友会の仲間に刺激を受けつつ、更なる社会貢献に邁進して参ります。
たしかに、安全配慮義務が契約の内容になっていますから、高齢者の方の転倒・骨折と施設の注意義務違反に因果関係があれば、賠償責任は認められます。
しかし、甲さんが異常がみられず、同じような状態であった場合には、施設としては注意する契機がありません。そこで、以前同じ行動をとったことがあるかがポイントになります。
そして、甲さんの初めてとった行動の場合は予見可能性がないので、特に手厚く見守りを行う注意義務もないものと考えられます。したがって、賠償責任が生じない場合もあります。
このように施設側の賠償責任のポイントは、
・施設側に過失がなく損害賠償責任がないと判断されること
・甲さんが初めてとった行動で予想できないこと
・今までにない事態が突然生じた場合は賠償責任なし
です。
また、福祉施設としては、正当の理由のない身体拘束は認められていないと指摘している点です。
しかし、判例がそうであっても「正当の理由」は、現実の安全との比較衡量でやや広めに解すべきようにも思います。
・身体拘束ができないから結果事故が生じた
というロジックも成り立ちますが、あまり共感は得にくいでしょう。むしろ、事故が起こる前に異常を察知して身体抑制をするべきだったといわれてしまうと思います。
本人の人格尊重も大事ですが、家族ともよく話し合って身体抑制は考えることが大事です。